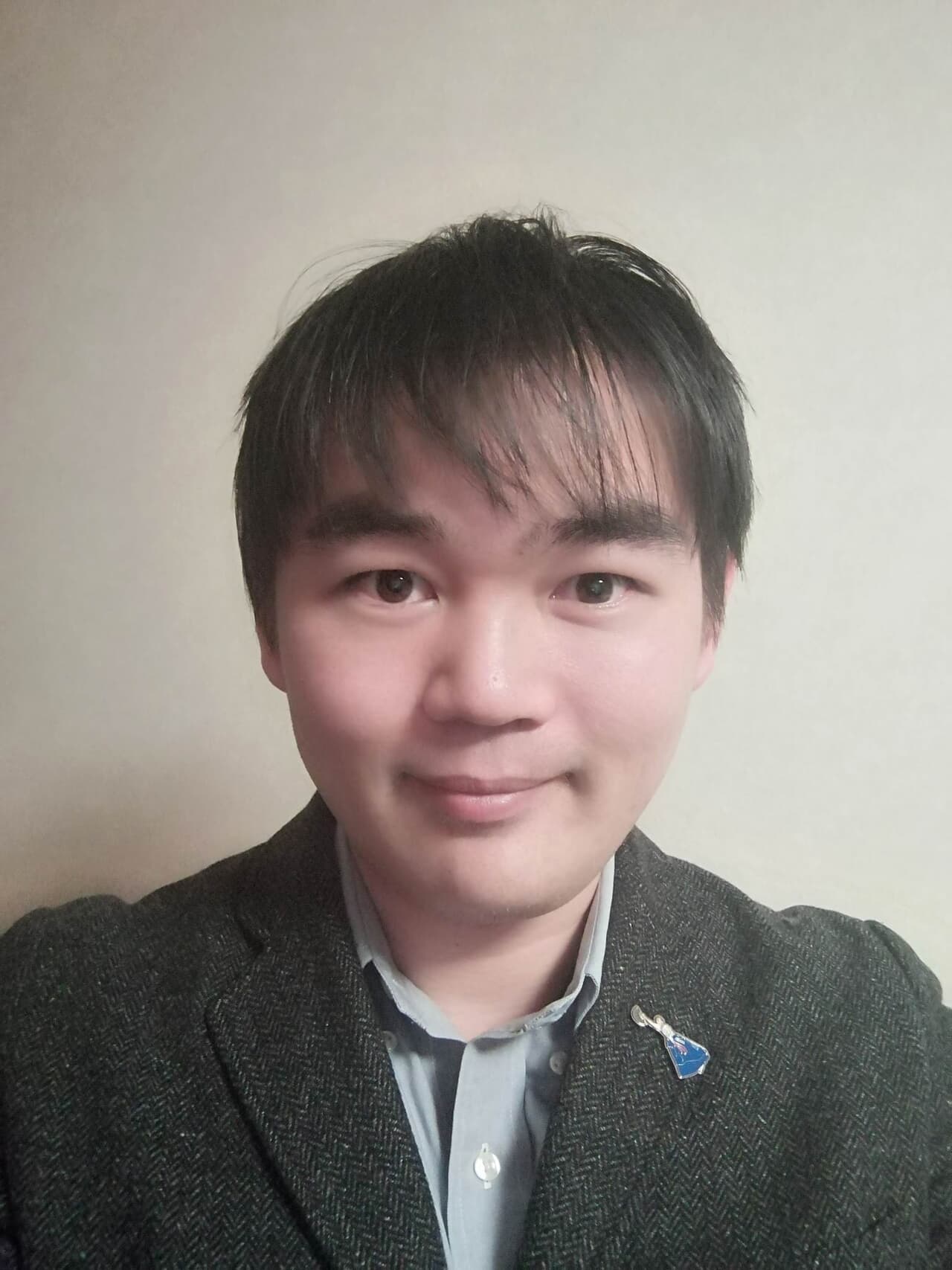思想家としての「小沢健二」入門

どうやら世間では「推し活」なるものが流行っているらしく、編集者さんから「推し活について記事を書きませんか!」という元気のいい打診をもらった。どうやら普段から私がちょっと変わった趣味の活動……例えばコーヒー好きが高じて定休日のカフェを借りてマスターをやってみたり、能を習ってみたり、学生でもなんでもないのに高校や大学の範囲の勉強をしてみたり……をしており、Facebookなどによく投稿していることが目を付けられたようなのだ。
しかし、こういった趣味の活動がいわゆる「推し活」かというと、それはちょっと違うように思える。
何を書いていいものか途方に暮れるが、ライターらしくまずは「推し活」という言葉の使われ方を考察するところから始めてみよう。
世間一般で言う「推し活」という言葉は、多分アイドルを応援することを起源とし、昨今は歌手、作家、あるいはスポーツ選手、場合によっては「行きつけのカフェ」みたいなお店まで含むこともあり……このような広い意味でのエンターテイナーを応援することと考えていいだろう。
さらに言えば、「○○のファン」という受動的な状態が、「推す」という能動的な行為として再定義されたことで、娯楽のただの消費者/受け手であることに留まらず、「応援することで、自分自身の生活が彩り鮮やかになる」ことまでを射程に捉えた言葉であるように思われる。「生活が彩り鮮やかになる」とは、例えば、日々の仕事に追われ生活に張り合いがない時、自分より若い歌手やスポーツ選手がストイックに頑張っている姿を「推す」ことで、「○○君/ちゃんがあんなに頑張っているんだから、自分も頑張ろう」と自分を奮い立たせるようなことだ。特にアイドルのファンにはこういう人が結構見受けられる。
「推し活」を、自分自身の考え方や行動も変化するくらいに誰かのことを応援したり、追いかけたりすることとして定義した時、その観点から私にとってもっとも重要な「推し」は誰か。
考えるまでもない。それは、小沢健二だ。
小沢健二より素晴らしいと思うミュージシャンは何人もいるけれど(小沢健二がミュージシャンとして素晴らしくないというわけではない。特に歌詞の良さとギターのアルペジオ奏法の巧さは出色だろう)、小沢健二ほど、創作物を通じて私に考え方・行動に影響を与えた人間は、本職の哲学者や思想家まで含めて他にいない。
これは私に限った話ではなく、私の観測範囲(ツイッター上での小沢健二のファンダム)では、彼のファンのかなりの割合が、ただ「好きな歌手」ということで小沢健二を推しているのではなく、ある種「人生の道標」みたいなものを彼に重ねている。
この原稿を書いている2023年1月現在、小沢健二のツイッターアカウントにはフォロワーが約15万人いるが、このうちの少なくない割合(少なくとも3割以上)は、小沢健二を預言者か、人生の師か、そこまででなくても信頼できる思想家/哲学者のような存在と考えているはずだ。かくいう私がそうなのだから、他の人もそうでないと馬鹿みたいじゃないか。
■いたいけな大学生がオザケン沼に落ちるまで
小沢健二のファンは、何が魅力でそれほどまでに彼を崇拝しているのか。
小沢健二を推しておらず、かつ90年代の活躍をなんとなく知っている世代の人は、90年代の「オザケン」に大体こんな印象を持っているはずだ。
「東大卒で、なよなよした雰囲気のいいとこのボンボン。歌はあまり上手くない」
小沢健二を熱狂的に推す私たちオザケンファンだが、この印象に関してはまったく否定しない。なよなよしていたことも、いいとこのボンボンであることも、歌があまり上手くないことも、すべて事実だ。(正確には、小沢健二は「小沢健二的歌唱法」の当代随一の使い手なのだが、「小沢健二的歌唱法」の評価軸は一般にいう「歌の上手さ」とは異なるので、「オザケンは歌がヘタ」と誤解されても仕方ないことはファンも認めざるを得ない)
それではなぜ、なんか雰囲気が鼻につくし、歌だって大して上手くない(と思っていた)小沢健二に、私たちは沼落ちしてしまったのか。
結論を言えば歌詞の素晴らしさに惹かれたからだが、例として私の沼落ち過程を紹介しよう。
90年代に小沢健二がテレビに露出しまくっていた当時、私は小学4~5年生で、やはり「歌手なのにあんまり歌上手くない。なんか有名な音楽家(小澤征爾)の親族らしい」くらいの印象しか持っていなかった。若い頃は誰しもものの道理が分かっていないもので、汗顔の至りだ。
転機が訪れたのは、小沢健二が一般に露出しなくなってから数年経った2003年、私が大学に入学した年のこと。私は、SHIBUYA TSUTAYAの当時地下2階にあったレンタルCDコーナーで、「そう言えば、高校の軽音楽部の先輩が好きだったな」くらいの軽い気持ちで、だいぶ年期が入り歌詞カードもよれよれだったフリッパーズ・ギターのアルバム『カメラ・トーク』(1990)を手に取った。家に帰り、借りてきたCDを自分用のCD/MDコンポにかけた瞬間から、私の人生はそれ以前とまったく変わってしまった。
「走る僕ら 回るカメラ もっと素直に僕が喋れるなら」(「恋とマシンガン」)
「花束をかきむしる 世界は僕のものなのに」(「午前3時のオプ」)
など、まるで自分の心のうちをそのまま覗いて具現化したような歌詞に、少年から青年へと移り変わるさなかにいた18歳の私は完全にノックアウトされてしまったのだ。
さらに言えば、フリッパーズ・ギターとして活動していた当時の小沢健二は東大の学生だったわけだが、私が入学した大学も東大だった。東大に入学してすぐのガキンチョは、往々にして高校の勉強が人より得意だった程度のことで天狗になるものだが、おかげさまで私の鼻は入学後すぐにへし折られたのだった。
駒場キャンパスのベンチに座り、MDウォークマンから『カメラ・トーク』を流し、夏の日差しを遮る青々としたいちょう並木を眺める。十数年前に同じ場所を、大体同じ景色の中を歩いていた時期に書かれたのであろう歌詞を聴きながら、
「小沢健二は、俺と同じくらいの年齢でこんな凄い歌を作っていたのか。俺なんてただの凡人じゃないか」と、今振り返ってもまったくもって正しい認識に至ったのだった。
それから、フリッパーズからの当然の流れとして小沢健二のソロを聴くようになり、「ぼくらが旅に出る理由」を一日に最低10回は聴く時期がひと月ほど続き、次に「さよならなんて云えないよ」を同じく最低10回は聴く時期が半月ほど続き……とオザケン漬けの日々が始まった。アルバムに収録されていなかったシングル曲を聴くために、ヤフオクで短冊CDのセットを定価の倍の値段で買い求めたりもした。般若心経を求めてシルクロードを旅した三蔵の気持ちが、少し分かった気がした。歌詞に描かれた世界がダイレクトに伝わってくる瑞々しい歌い方にも、いつの間にか惹かれるようになっており、ただ音程が合っているだけの歌手をつまらなく感じるようになった。
……以上が私がオザケン信者になった経緯だが、私のような後追いファンは大体似たような経緯を辿っていることだろう。